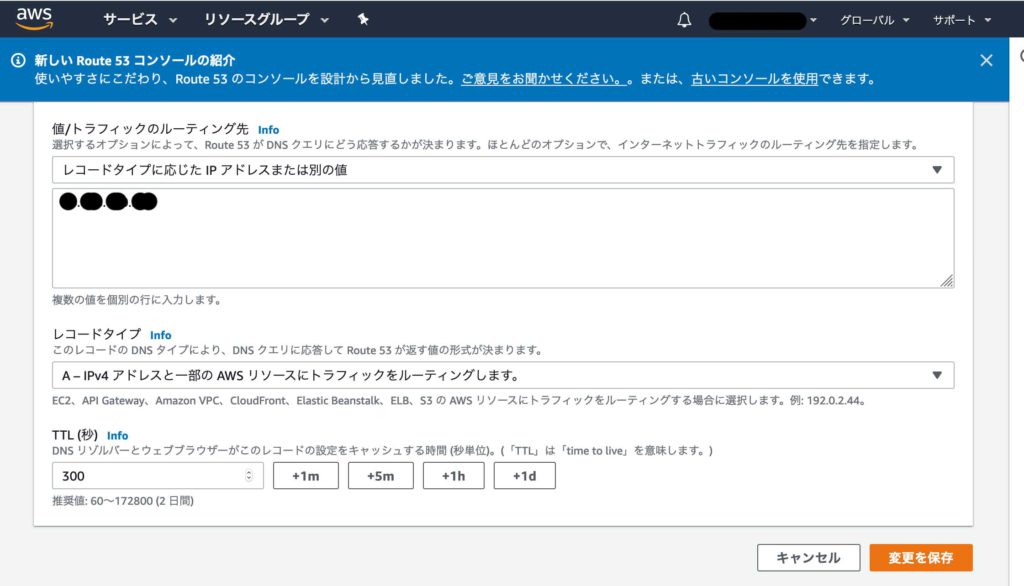以前お世話になった苅田ディレクターと中井プロデューサーが担当していたので、じっくりと2回ほど見た。
不謹慎だがと断って研究者が述べていたように、福島第一原発事故から10年たって低線量被曝が野生生物、ひいては人間に対してどのような影響があるのか、期せずして壮大な実験圃場となっているのは間違いない。私も正直なところ被曝がどのような生理学的な変化をもたらすのか興味がある。
番組では、原発事故に翻弄されながらも調査に協力する被災者らの人間的な側面もあわせて描いている。まだNHK+で見られるのでぜひ見てほしい。
野生動物に占拠されてしまった帰還困難区域
野生動物が街中を闊歩し無人の家を荒らす映像によって、自然が秘めたたくましい生命力を見せつける。被災者には悪夢のような光景だが、ドローンによる無人の帰還困難区域を映した映像が美しく印象的だった。空撮による移動ショットの中で、時間経過をフェードで表現するなど凝った映像も多かった。
またキツネとイノシシが接触しそうになる映像もあった。基本的に別種の中型哺乳類が、野生の環境で遭遇するのを見かけることは極めて稀であり、野生動物の密度が高まっていることを象徴するシーンである。
もちろん注目すべきは映像のすごさだけではなく、福島第一原発事故から10年経過しての放射能被爆の生物への影響評価をコンパクトにまとめてくれていることである。以下にまとめる。
不気味な変形を見せる針葉樹
原発事故の後2〜3年の間に芽吹いたアカマツに限って枝分かれが非常に多い異変があったことが、福島大学のヴァシル・ヨシェンコ先生らによって確認された。なぜか幹が発達しない。マツの他3種類にも事故直後に異変が見られた。帰還困難区域のアカマツはオーキシンの濃度が低くなることが原因と考えられている。
放射能による汚染は目に見えず被害が分かりにくいのが特徴だったはずだが、目に見えて形に異常をきたしていることが分かるのは非常にインパクトが大きいといえる。
山にいなかったはずのクマが出現
東京農業大学の山崎晃司先生らの調査で、浪江町のセンサーカメラに、阿武隈山地周辺では生息しないと考えられていたツキノワグマがこの3年で3回、捉えられた。2020年7月、飯舘村の林道でツキノワグマの親子に遭遇した地元の人の映像で、このエリアではじめて子育てが確認された。繁殖の中心になる集団が阿武隈山地に定着している可能性が高く、増えて分布域を広げるのは確実だという。ツキノワグマは10年で5倍に増える繁殖力をもっていて、今後も人里を脅かしかねない。
ちなみに阿武隈山地のセンサーカメラで高標高地に外来種のアライグマが見つかっていることも分かった。コロナ禍で少し人が外に出なくなると、すぐに動物たちが進出してくるのは世界共通の現象であり、昨年は北大でも久しぶりにエゾシカがキャンパスに入り込んだ。キタキツネも街なかに姿を見せるようになってきている。
初期被爆のサルに癌化などの兆候は現時点では見られず
東北大学の福本学先生のニホンザルの初期被爆に関する調査。サルの寿命はおよそ20年なので10年経過したサルの体内で起きる変化は人への影響を推測しやすい。
2021年2月有害駆除されたニホンザル648匹目の解剖の様子も紹介されていた。空気や餌から大量の放射性物質を取り込んでいた。甲状腺には放射性ヨウ素131が集積し、癌の原因となるが、半減期が8日と短いためヨウ素131はすぐ消えてしまう。そこで半減期の長いヨウ素129に目をつけた。原発事故で22(ヨウ素131)対1(ヨウ素129)の割合で発生したと推測されている。
ヨウ素129を使って、初期の被曝量を7匹で推定したところ、汚染された餌によって1000ミリシーベルトに達した高い被爆をしていたと思われる3匹がいた。しかし、甲状腺の細胞組織を精密に分析したが、今のところ癌は見つかっていない。
サルの染色体に異変見つかるも回復傾向
弘前大学の三浦富智先生は、サルの染色体に異変を見つけた。2つの色が混じり合ってるように見える。切断された2本の染色体が入れ替わって再結合した「転座」と呼ばれる異常で遺伝子を変異させることがあるという。染色体で遺伝子の変異が蓄積し続けると、細胞が癌化するリスクがあり、非汚染地域に比べ2.5倍の頻度であった。
だが、その発生頻度は最近になるほど減少していて、回復しつつある。これもまた野生動物のもつ生命力というものなのかもしれない。
被爆したイノシシも環境に適応しつつある?
宮城大学の森本素子先生はイノシシの免疫への影響を調べている。旧避難指示区域のイノシシは汚染されていない兵庫県のイノシシと比べ、免疫を強化するサイトカインという物質の関連遺伝子が10倍活発になっていた。
慢性的な低線量被爆を繰り返すイノシシの体内では、小腸の内側の無数の免疫細胞には放射線によるストレスが常にかかる。遺伝子は免疫活動を強化するためにサイトカインを作る司令を出す。
サイトカインが暴走するとかえって体にとってはリスクとなるが、イノシシの小腸では現時点では目に見えるような変化は起きていない。放射線の影響は受けているが、生理学的な範囲では対応できているという状況だという。これもまた生物の適応力なのだろうか。
ネズミの精原細胞が増えている
新潟大学の山城秀昭先生によると、被曝量が多いアカネズミほど精原細胞が増えていることが分かった。よく見ると精原細胞は二層になっていて、被曝量が少ないネズミより数が多い。低線量の刺激で何らかの増殖機能が働き増えたようで、種を保つための反応といった生命現象の一つだと思われる。だが最終的にできた精子の数と受精能力は被曝量に関わらず、変わらなかったそうだ。
被ばくの森の今後
東京農業大学の上原巌先生は、事故直後から汚染された森林の再生について研究してきた。注目しているのは新たに芽吹いた樹木。日陰に強い樹木が生えてきていて、セシウムはほとんど含まれていないことが分かった。セシウムは土壌に強く吸着され、根からの吸収が抑えられているのかもしれないとのこと。一時は絶望視されたが、被爆の森における一つの希望として紹介されていた。
故郷を奪われながらも調査に協力する被災者たち
住む家や土地を汚され、仕事も奪われた被災者らの絶望は、お金で解決できるものではない。せめて科学的な調査には協力しようと尽力してくれている姿には本当に頭が下がる。
人生を賭けて森を育てきた林業家や、被爆した牛を見捨てずに世話してきた酪農家。もう出荷できない放射能に汚染された牛だが安楽死させるのはかわいそうだと、研究のサンプルに提供することもあるという。
原発事故後、駆除されたイノシシは6万頭に達した。イノシシによる被害は大きいが、檻の中にいる小さな子どもを殺す時は本当に涙が止まらなかったという猟師の言葉は重い。動物たちもまた被害者だ。
研究者は「汚染地の状況は50年、100年先を見越してどういうふうに向き合っていくかが必要だ」と語っていた。放射性廃棄物は処理に何万年もかかり、こうした科学者らによる継続的な研究が生かされる日がくるのかもしれない。
2021.5/11






.png)